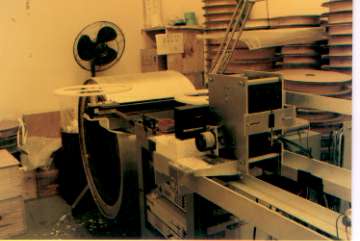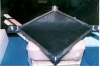τニュートリノ検出実験とファイバートラッカー
最新更新:2001年12月3日
2000年7月20日、米国フェルミ研究所は4つのτニュートリノを確認したと発表しました。
この実験は1995年から準備していたもので、名古屋大学のF研を中心とした日本のチームとフェルミ研究所の協力で実現したものです。
7月21日の各新聞に掲載された記事を紹介します。
| 朝日新聞夕刊 | 中日新聞夕刊、赤旗新聞 |
 |
 |
この実験で中心的な役割を果たした「ファイバートラッカー」の実用化や原子核乾板を精度よくビームライン上に設置するアイディアは金工室の独自のものです。
τニュートリノ検出で活躍したファイバートラッカーの一部は、瑞浪のサイエンスワールドに展示され、宇宙線観測のデモンストレーションを行っています。
τニュートリノ検出実験とは
米国のフェルミ研究所(FNAL)で行われたτニュートリノ直接検出実験(E872/DONUTS)は、名大理学部物理F研が中心となって進めた国際共同研究です。
1999年のニュートリノ国際会議においてカミオカグループがニュートリノに質量のあることを発表し、名古屋グループがτニュートリノを検出したと発表したことで、ニュートリノに関する研究がにわかに脚光を浴びました。この二つの報告は相補完するもので、今後の研究課題がニュートリノの質量決定に向かう転機となりました。
2000年7月20日、米フェルミ研究所はこの実験において4つのτニュートリノを確認したとの最終的な発表をしました。これによって、直接確認されていなかった最後の基本粒子「τニュートリノ」の存在が明らかにされました。
E872の主力検出器は原子核乾板とファイバートラッカーです。
ファイバートラッカーはコーラス/CERNの実験で理学部装置開発室と共同で開発したもので、今回のE872も同様に装置開発室と共同で作ってきました。
もう一つの重要なディテクターである原子核乾板(エマルジョン)は名古屋大学のF研が世界をリードする技術開発を行い、素粒子実験の強力なディテクターとして育ててきたものです。
E872における物理金工室(河合)の役割は、ミネソタ大学の技術スタッフと協力して原子核乾板とファイバートラッカーをビームライン上に精度よく設置するための設計を担当すると共に、原子核乾板ホルダーの設計製作、ファイバートラッカーを精度良く設置する技術開発を行ないました。FNALの現地作業にも参加し、組みあがったディテクターをビームライン上に組み立て、設計意図の通りに組みあがっていることを確認してきました。
ファイバートラッカーの読み出し端末処理は装置開発室の石川さんが担当し、実際に読み出し装置との結合機構の開発は金工室の松岡さんが担当しました。
この実験はトリガーカウンターの読み出しに特殊な光学系を用いました。これはアクリル樹脂を装置開発室の超精密旋盤で加工したものです。この加工は装置開発室の小林さんが担当しました。
Return to top
ファイバートラッカーのインストール(米国・フェルミ研究所にて)
名古屋大学で製作したファイバートラッカーは厳重に梱包し、米国・フェルミ研究所(FNAL)に送りました。
フェルミ研究所では、2週間を、2回にわたり作業することになりました。特に二回目は百武彗星がまだ夕方の空を飾っている磁気であり、強く印象に残りました。
以下に、フェルミ研究所での組み立て作業の様子を写真で紹介します。
現地に到着後、重機(クレーン等)の手配ができるまで少し時間があきましたが、その間、インストールの手順を考えることができました。
現地での作業条件や工具類の確認なども重要な作業です。海外の作業で一番泣かされるのはJIS規格(日本の工業規格)の工具やねじなどの部品が足らなかったときに現地で入手できない時です。そのようなことを想定して、あるていど余分に部品を持っていくのですが、見落としや気付かないことは必ずあって、現地を探し回ったあげくみつからず、その作業をすすめられなかった・・・という苦い経験をする羽目になります。
| ピットにクレーンで搬入 | ピットに降ろしたファイバートラッカー |
 |
 |
ファイバートラッカーを載せる架台はミネソタ大学のデラ・コバさんが作ってくれました。大きな円筒状のものはIITを磁気シールドするためのもので、構造用鋼管を用いました。IITのインストールやメンテナンスが楽にできるように、ウインチを用いた上下駆動機構が備えられています。
今後、ファイバートラッカーをこの架台で数年間動かないように保持する必要があります。原子核乾板の取り替え作業など、重量物を取り扱うので、ファイバートラッカーの架台と原子核乾板搬入の踏み台とは別構造とし、ファイバートラッカーが動かないよう設計されています。これらはデラコバのアイディアです。架台が組みあがったところで、ビームライン上の正しい位置に基準点があるかどうかを測量で確認ました。この時の読みとり精度は0.1mmです。
| ファイバートラッカーを載せる架台を組立るデラ・コバ | 組立後の位置精度をトランシットによって測定する |
 |
 |
ファイバートラッカーの架台にはもう一つの重要な役割があります。それは、ファイバートラッカーと全体を厳密に遮光することです。
ファイバートラッカーはファイバー自体がチェレンコフ発光をするとともに、受光素子であるIIT(暗視野カメラ)まで光を導くのですが、ここまで届く光は極めて微弱であり、検出限界に近いものなのです。
| ファイバーが接触しそうな場所はソフトロンを貼る | 遮光壁の外側にさらに遮光シートをかぶせる |
 |
 |
読み出しのIIT(暗視野カメラ)と磁気シールドの組み立ては写真のように架台の下に潜り込んで行うことになります。左右に45度傾いているIITは取扱も楽ですが、真下に配置されているIITの磁気シールド用鉄パイプは、そのままの長さでは床と干渉して取り外しができないので、短く切断し、ネジで互いに連結するという凝った構造となっています。
| 左右の45度傾斜した磁気シールド用鉄パイプ | 真下にある分割型の磁気シールド用鉄パイプ |
 |
 |
下の写真はファイバートラッカーの下流側半分をインストールしたところのものです。このように、上流と下流の二つのブロックに分けています。
| 上流側左から見たところ | 真正面から見たところ |
 |
 |
IIT(暗視野カメラ)をインストールしたところで、動作試験を行ない、初めてIITの信号を確認したところです。
| IITの遮光 | 初めてIITの信号を見る | 動作条件を調整し綺麗な映像を得ることに成功! |
 |
 |
 |
順次インストールが進み、最終的に組みあがったディテクターはこのような金属製の遮光ボックスに覆われます。
| 下流半分を無事インストール | 全てのファイバートラッカーをインストール | 架台の蓋を閉めたところ |
 |
 |
 |
FNALの山之内先生(当時、副所長)は時々我々の実験準備の様子を見に来て、励ましてくれました。
| 準備の進行状況を報告 | 装置を見てもらいつつ、説明する中村氏 |
 |
 |
ファイバートラッカーと原子核乾板の間にトリガーカウンターを組み込みました。
トリガーカウンターを組み入れる
| トリガーカウンターの組立 | 組みあがったトリガーカウンター |
 |
 |
参考資料
- Research and Development of Scintillating Fiber Tracker νμ−μτ
Oscillation Experiment/KAWAI et al.,
/IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE Vol.39,No.4 P680〜684/1992
- 加速器実験用ハニカムボードの製作/河合/技術研究会報告No,15 P13〜16
/1996.7./分子科学研究所
- 三次元CADによるニュートリノ実験のターゲットデザイン/河合
/技術報告 VOL.7 P77〜84/1996/名古屋大学理学部
- フェルミ研究所見聞録/河合/技術報告 VOL.7 P33〜37/1996/名古屋大学理学部
Return to top
ファイバートラッカーの開発
ファイバートラッカーは細い(直径500μm)プラスチック・シンチレイション・ファイバーを規則正しく並べたもので、世界に先駆けてF研・装置開発室・物理金工室が共同で開発した素粒子飛跡検出装置です。
ファイバーを規則正しく並べる技術で最も重要な役割を果たす大口径のドラムの製作に関する技術開発と、並べられたファイバーの精度を測定する大型二次元座標測定器の開発を行い、CERN/CHRUS、FNAL/E872で用いられているファイバートラッカーの製作に協力しました。我々が開発したファイバートラッカー製作技術は、KEK/E362(つくば神岡間・長基線ニュートリノ振動実験)でも採用されています。
ミネソタ大学の作った架台に精度良く載せるためのしくみは三次元CADで設計しました。また、一定の間隔で並べたシンチレーションファイバーをファイバートラッカーとして用いるには精度の良い平面に基準穴をあけて、それを全ての位置決めに使うことで、全体としての精度を保つ機構になっています。
基準面は素粒子が通過するので物質量の少ない紙ハニカム構造とし、自作しました。この基準面も基準穴の位置精度を得るための工夫がしてあります。
下の写真は、シンチレーションファイバーを等間隔に並べる上で最も基本的で重要な部分です。
シンチレーション・ファイバーを、糸巻きのように等間隔でドラムに巻き付けていきます。このとき、ドラムにはファイバーの間隔と同じ感覚の溝が切ってあり、ちょうど糸がその溝に降りていくように回転しながらファイバーを巻き取っていきます。
最初に並べた一層分を樹脂でかためた後、その上に同様にシンチレーションファイバーを巻いていきます。下の層より上の層の張力を大きくします。これは、最後に切り取ってドラムから外したとき、その張力の違いによって真っ直ぐな板状にするためです。
| シンチレーションファイバーをドラムで巻き取り、ファイバーバンドルを作る準備の進行状況を報告 |
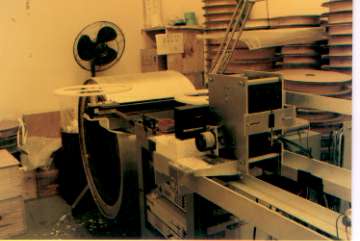 |
ファイバーバンドルを平面に並べるための背板(基準面)は、素粒子との相互作用が少ない物質でしかも長期間位置精度を保てるものでなくてはなりません。私たちは、紙に樹脂を含浸させたハニカムコアを薄いガラス繊維強化エポキシ樹脂の板で挟んで接着した特別製のハニカム板を基準面に採用しました。このようなものは市販されていないので、自作することになりました。
基準面となるハニカム板(複数)を精度良く作るには、下の写真のような上下のプレス板と、それぞれの位置あわせとなる基準穴+テフロン製の軸です。プレス板には位置精度20μm以内(普通にNCフライスで穴の位置決めを行えばこの精度は簡単に実現します)となるよう基準穴を設け、そこにテフロンの軸(僅かにプラス公差)を押し込むことで、接着剤が硬化する間も基準穴がずれないようにしています。
| 基準板とハニカム板の枠材 | 基準板に表面板(ガラスエポミシ)と枠材を並べたところ | 押さえ板を載せ、テフロン軸を通したところ |
 |
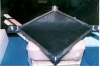 |
 |
次に、ドラムに巻いて作ったファイバーバンドルをハニカム板に接着します。この時、バンドルが基準穴から同じ位置に来るよう、治具をあてて位置決めをします。
| 治具にテフロンのピンを通して位置あわせを行う | おもり板を乗せて接着しているところ |

| 
|
ハニカム板に接着したファイバーバンドルの直線性や基準穴からの位置を測定し、トラッカーの基礎的なデータとして保管します。
| 自作の大形二次元座標測定器でファイバー間隔精度と直線性を測定 | 接着したファイバーシートの平面精度を測定 |

| 
|
ファイバーバンドルを接着したハニカムボードを重ね、ファイバーバンドルの端末を少しずつまとめて、治具で接着していきます。
| ファイバートラッカーを所定の間隔に配置 | ファオバーの端末をまとめて接着 |

| 
|
順次重ねていき、予定の枚数を重ねたところ
| 全てのファイバートラッカーを所定の間隔に配置したところ |

|
ファイバーバンドルの端末をすべてまとめ接着、端面を研磨する。
| 横フライス盤にて端末を切削・研磨 | 仕上がったファイバーバンドルの端末 |

| 
|
こうして全てのファイバーバンドルが基準となるハニカム板に並べられ、基準面の間隔がスペーサで正確に決められると、ようやくトラッカーの完成となります。
| 完成したファイバートラッカー |

|
参考資料
- シンチレーティングファイバートラッカーの開発研究/河合他/
放射線 Vol.12,No.3 P85〜119/1995
- Mass Production of Multilayer Scintillating Fiber Sheets for
CHORUS Neutrino Oscillation Experiment/KAWAI et al.,/
Scintillating Fiber Detectors 1995/World Scientific Publishing P525〜533
Return to top