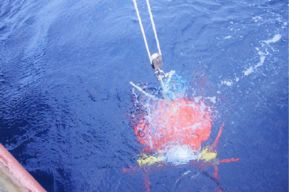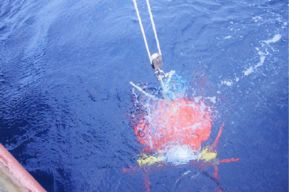自然情報技術班
菅島臨海実験所 村田 明、 砂川 昌彦
生命理学専攻 小川 和子、 西岡 典子
地震火山観測研究センター 中村 勝、 宮島 力雄
奥田 隆、 山田 守
(技術部組織図によると極限分析技術班)
1.菅島臨海実験所
三重県の伊勢志摩島国立公園内にある鳥羽港外に位置する周囲12キロの菅島にある。当研究所は生物のみならず、他の広い分野の海に関する科学研究の場たることを願い、名古屋大学の学生・研究者のみならず、事情の許す限り他の大学・研究所の学生や研究者の利用をうけいれている。研究として、アポトーシスの分子機構、運動に関わる分子機械構成分子の機能、環境変化に対する応答としての観点から捉える夜光虫の発光に関する情報変換機構が対象となっている。これらの研究に供する生物実験材料の捕獲および実験の補助を行うとともに、近年減少している研究材料としても重要なウニの養殖、産卵期の人工的調整の研究を技官を主としておこない、成果をおさめている。また、菅島という離れ島に立地している為、人や物の運搬が必要である。それらは技官が担当しており、2名共に船舶運転免許をして操船すると共に、船舶の維持、管理を行っている。
業 務
- 実験・研究の補助
- 学部・大学院生の実習指導補助(臨海自習・海洋実習・磯採集・海洋生物の分類指導など)
- 実験設備の維持管理
- 実験所周辺の環境整備
- 研究・実験・測定・分析・検査・実験装置の試作および設計
- 船舶の操船・維持・管理
2.生命理学専攻
生命原理を明らかにする目的で分子および細胞レベルで研究がおこなわれている。大腸菌、ラン藻、酵母、線虫、ショウジョウバエ、ゼブラフィシュ、メダカ、マウス、シロイズナなど、分子遺伝学で用いられているほとんどすべてのモデル生物を研究材料としている。学生実習担当技官はこれらのほとんどの材料を用いた多種多様の学部学生実習の準備、実習等をおこなっている。また、所属研究室での研究補助もおこない、研究発表をおこなうなど研究にも貢献している。遺伝子発現制御額グループに所属している技官は所属研究室の大腸菌を用いた環境に応答したタンパク発現制御調節機構についての研究補助をおこなうとともに理学部・理学研究科等放射線取り扱い主任者として放射性同位元素の管理にあたっている。平成11年2月25日に科学技術庁の立ち入り検査があり、指摘された件について改善する作業をおこなった。平成12年の放射線障害防止法関係法令の改正時、それに伴う理学部規則の改定作業をすると共に、文部科学省への申請書を作成し申請した。
- 学生実習担当技官
- 生命理学科2および3年生の学生実習指導
- アイソトープ管理区域の汚染検査
- 生命理学共同利用の電子顕微鏡の保守・管理
- 遺伝子発現制御額グループ所属技官
- 理学部・理学研究科等放射線取り扱い主任者
- 10Sa RNAの構造と生理学的機能の研究
- 学生・大学院生の実験指導
3.地震火山観測研究センター
当研究施設は1965年第一次地震予知計画開始と共に、犬山地震観測所が新設されたのにはじまる。犬山地殻変動観測所、地震移動班、高山地震観測所、三河地殻変動観測所がつくられ、1975年には東山キャンパスに地震予知観測地域センターが設置される。その後、測地移動班が増設され、1989年には火山部門が新設されると同時に犬山、三河の各観測所がセンターに統合される。又、1998年には高山地震観測所がセンターに統合され、同時に海底地殻変動部門が新設された。現在センターに教官11名と技官4名の形態となった。
名古屋大学の地震観測網は中部地方地域に展開されている。そのデーターはテレメーターにより東山キャンパスのセンターに常時集中され、自動処理システムに取込まれている。このシステムは大学間のデーター流通、気象庁へのデータ転送など地震予知体制に組込まれている。地震観測のほか、当センターでは御前崎から北西方向に延びる長さ約140Kmの地殻活動総合観測線の展開、レ−ザー光線を使用した光波測距、人工衛星を使用したGPS観測による測量、水準測量、および重力観測など多項目にわたって地殻変動観測を実施している。また、海底地震、海底地殻変動の観測も実施している。さらに地球科学教室と協力して、地球化学的観測、移動観測班による研究観測など、この地域の地震発生と地殻活動、地球内部構造との関連性、地震先行現象の検出を目的とした観測など、地震予知のための基礎的研究がおこなわれている。
火山関係では、火山現象の解明に向けた基礎研究と火山噴火予知を目指した観測の課題に取組んでいる。基礎研究では、噴火機構の物理学を解明する目的で実験を行なうと共に実際の計測のための機器開発を行なっている。観測研究では、焼岳や木曽御岳の活動の各種観測を通じて火山活動の機構解明と火山噴火予知の研究につとめている。
さらに全国の大学が参加し、人工地震による地下構造探査、地震の多点観測による 精密地震活動の研究、GPS測地測量、火山体の地下構造探査のための多点地震観測 等が行なわれる。
以上のように大変幅広く各種の技術が要求されている。これらを4名の技官が教官と共にそれぞれ役割を分担し対応している。また国内の観測ばかりでなく海外の観測にも参加することもある。これらの仕事をするために年間平均100日前後の出張をして対応している。
その主な仕事を以下のようにまとめてみた。
- 地震火山観測地域センターテレメーター綱の維持管理
- 地震、地殻変動、火山活動の各種観測および観測計器の開発、製作
- 各種観測データーの作成、解析
- その他
神津島の水準測定(2001年3月)
(地面の上下変動を0.1mmの精度で測量する) |
 |  |
| GPSによる地殻変動検出 | 海底地殻変動観測システムの開発 |
 | 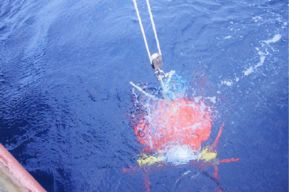 |