岩石中における微小空隙同定手法の開発とその意義
*名古屋大学博物館・理学研究科 吉田英一
1.はじめに
地下地盤を構成する地層や岩石中には、目に見える割れ目などの空隙だけでなく、非常に微細なサイズの様々な形を有した空隙が存在する。このような微小スケールの空隙は、地下岩盤中の地下水が移動する経路となるだけでなく、地質環境中の汚染物質などの地下水に溶け込んだ物質を吸着させたり、固定したりする役割を果たすものとしても注目されるものである(Yoshida et al.1994)。これらの微小スケールの空隙構造は、しかしながら、これまでの光学的な手法では観察することが困難であり、また試料形成途中での二次的(人工的)な空隙とも区別する必要性から、観察のためのあらたな手法の開発が求められている(與語ほか、2001)。
ここでは、先に本報告書の與語(2002)で示された手法の活用方法と、その意義について主に述べる。
2.岩石中における微小空隙同定手法開発の背景
岩石は、堆積岩にしろ、火成岩にしろ基本的には鉱物の集合体である。これらの鉱物の集合体で形成されている地下深部の岩体中に、現在、さまざまな廃棄物や有害物質の処分が検討されつつある。それらの1例である放射性廃棄物は、地下約数百〜1000メートル程度の地下に埋設処分されることが1つの将来的な手法として考えられている(Savage,1996)。このような地下処分を行う場合に、その安全性や処分後の環境モニタリングなど、どのように実施していけばいいのかについての研究開発が進められつつある。その中でも、とくに重要視されているものの1つに、有害元素の地下水中への混入による地下岩盤(岩石)との反応プロセスがある。放射性廃棄物の処分の場合、放射線の影響が半減期によって人体に影響がなくなるレベルまでの期間が約数万年〜数十万年と見積もられている。したがって、これらの長期的な期間を、反応プロセスの評価期間として考えることが求められている。
このような長期に亘る評価を行う場合に重要なことは、反応が生じると考えられる「場」の同定とその「量」や「空間的構造」の厳密な把握である。例えば水などの移動する経路面積の総量が1桁異なれば、時間ごとの反応の見積もり量も最低1桁異なることとなり、最終的な安全性の見積もりの幅もこれに伴って大きく変化することとなってくる。このような見積もりのズレは、経済的なコストにも大きく影響を及ぼすこととなる。このような背景に基づいて、現在、岩石中に存在する微小空隙同定手法の開発を極限技術班と共同で実施しているところである。
3.調査内容と主な結果
実際に行った微小空隙の同定結果は、本報告の與語(2002)でも示しているが、基本的には約幅1ミクロン程度のものであれば、染色/蛍光レジンの注入によりほぼ同定可能であることが示されつつある(図1a,b)。
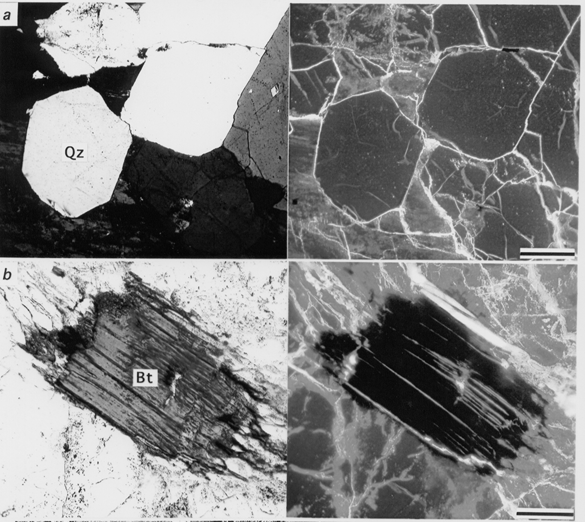 |
図1:a) 岩石(花崗岩)中の石英(Qz)粒子(左)とその境界および粒子内に存在する染色試験によって確認できる微小割れ目(右)。b) 同様に岩石(花崗岩)中の黒雲母(Bt; 左)内に発達する染色試験によって確認できる空隙(右)。スケールは100ミクロン。
これらの数ミクロン以下というスケールの微小空隙研究の延長上として、具体的にそういった場所でどんな現象が生じているのかの調査も行っている。これらの微小空隙中が、有害元素にとってどんな場所(例えば化学的あるいは物理的反応の場)となり得るのかについては、厳密な手法で空隙の状態を把握したあとは、さまざまな自然現象との組み合わせで理解する他はない。そのような観点から最近得られた結果のいくつかを次に紹介する。
図2は、岩石中の微小空隙内に認められた構造の電子顕微鏡写真である。小さな繭状のものが集合している様子が見てとれる(左)。その拡大(右)では、その繭状そのものの大きさが約1ミクロン程度のものであることがわかる。
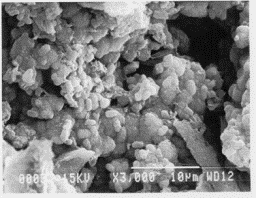 |
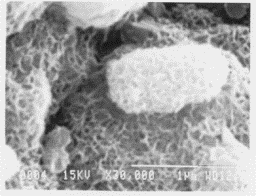 |
||
図2:岩石の空隙内に見られる繭状の集合体(左)とその拡大(右)。繭状の個々の大きさは約1ミクロン。
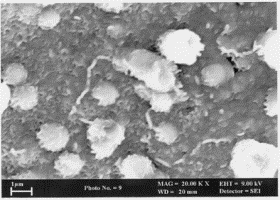 |
図3:繭状のものから伸びるひも状の構造。おそらくこれらの1つ1つが微生物で、繭状のものはこれらのコロニー状の集合体と考えられる。
4.手法開発の重要性
今回ここで示した結果は、基本的にはこれまでの技術の延長上の成果として得られたものである。しかし、様々な現象の長期的な評価や予測を将来的に行う場合、その精度を上げるためには現有技術をいろいろな意味で高度化し、分析や測定の精度をより高めていく他にない。岩石内部の状態を理解するにおいても、技術の向上は不可欠であり、その技術なしには地質環境中でのミクロン〜ナノミクロンスケールでの現象理解は不可能である。
今後は、これらの技術をベースにさらに精密な調査分析を行っていくとともに、三次元的な空間分布の調査手法の開発も行っていきたいと考えている。
5.文 献
Savage,D.,
1995: The scientific and regulatory basis for the geological disposal of
radioactive waste, John Wiley & Sons Press, pp.321-353.
與語節生、2002: 岩石中の微小空隙構造の同定手法の開発(本報告資料)
與語節生・吉田英一・山本鋼志、2001:染色法による岩石中微小空隙構造の同定とその特徴。名古屋大学博物館報告、No.17,
pp.7-13.
Yoshida,H.,
et al.1994: Flow-path structure in relation to nuclide migration in sedimentary
rocks, Jour. Nuclear Science and Technology, Vol.31, No.8, pp.803-812.