岩石薄片による微小空隙同定・手法の開発
極限技術班 與語節生
はじめに
岩石中には、さまざまな空隙(隙間)が存在する。これらの空隙は岩体中を移動する地下水や、地下水によって運ばれる溶存物質(元素など)の移動経路として重要な機能を果たすことが最近の調査で明らかになってきた。また移動経路としてだけでなく、溶存物質(元素)の吸着の場としても重要な役割をなすことが指摘されている。
このような空隙構造の働きは、環境問題の1つである高レベル放射性廃棄物など、地質環境中に埋設し、生活環境から隔離する際に、埋没物質が生活圏へ漏出しないために重要な働きをするものと考えられている。岩石中の微小空隙構造のこれらの働きを定量的に評価するためには、その特徴や・サイズ・分布・量を明らかにすることが不可欠である。この様な研究目的から、空隙構造の観察のための岩石薄片作製の手法を開発した。
1. 手法の開発の目的
岩石中の地下水や溶存物質が移動すると考えられる数十から数ミクロン以下の微小空隙構造を確認し、その特徴を明らかにするために、岩石中に存在する空隙のみを抽出・観察する手法の開発を目的とする。今回は既存の樹脂や染色剤等を用いた、簡便な調査方法の開発を試みた。微小空隙構造の同定法について、従来の方法のみでは、マイクロクラックや微小空隙が調査・観察のための岩石薄片等の作成過程で生じたものか、識別が困難な状況にある。従って、これらの要素を取り除くために、何らかのマーキングを行う必要がある。
2.実施内容・試験方法
岩石中の微小空隙(割れ目)の観察には、粘性が低く、浸透性がよい樹脂に、染色剤及び蛍光剤をメチルメタアクリレートに添加し試料に浸透させる試験方法を採用した。
この種の方法は、土木工学の分野で主にコンクリートの強度試験、マイクロクラックの発生や物理的破壊現象を同定等のために開発されつつある手法である。注入工程と岩石の薄片作製手順は、以下の通りである。
(1)
内部空隙構造を調査したい岩石試料を準備する。岩石試料の加工作業による人為的なダメージを受けていない試料が重要である。
(2)
岩石試料を40~50℃の低温で数日乾燥させる。
(3)
岩石試料をビーカー等の容器に入れ、レジンに浸す。
(4)
デシケターで減圧し2~3日程度放置する。(岩石中にレジンの浸透を促す)
(5)
放置後、ビーカー供に60~80℃程度に加熱し、レジンを固化させる。岩石の空隙率が高い場合は、小さい気胞の発泡が生じ、固化作用を妨げることがある。従って空隙率の高い岩石は、60℃前後の温度で長時間かけて固化させることが望ましい。
(6)
固化後、岩石カッターで切断し、岩石試料内部の薄片を作製することで岩石が有する本来の空隙構造調査に供する。
(7)
作製した岩石薄片を、偏光顕微鏡と水銀ランプ発光の蛍光装置とお組み合わせた紫外線発光観察装置で観察する。
これらの注入工程と岩石の薄片製作手順を図1に示す。
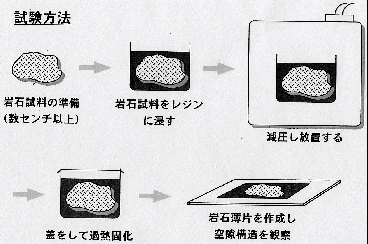
図1 染色試験方法の概念図
3.
岩石薄片製作手順
通常の薄片製作行程は、前半の第1次研磨と後半の第2次研磨とに分ける。第1次研磨は、試料のチップを、スライドグラスに接着するまでの研磨行程で、第2次研磨はスライドグラスに接着した試料を、厚さ0、02㎜~0、025㎜に仕上げる研磨行程である。
1)チップ(試料小片)の整形
岩石薄片のスライドグラスの規格から、チップの整形は24㎜×32㎜×5~10㎜が普通薄片には一般に利用されている(図2)。
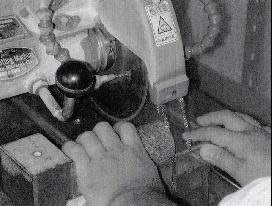
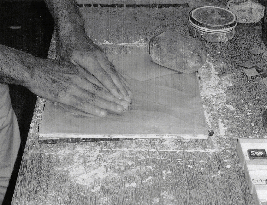
(図2)ダイヤモンド切断機 (図3)メノウ板、3000#での研磨
(チップの整形・2次切断) 研磨面は鏡面に仕上がる
2)第1次研磨
岩石研磨機を用いて、カーボランダム120#と、・400#の順に研磨する。次に研磨用の鉄板、600#カーボランダム・ガラス板、1000#アランダム・メノウ板、3000#アランダムで、順に研磨する。研磨面はこの段階で鏡面に仕上がる(図3)。
3)スライドガラスに接着固定
マルトーKKのペトロポキシ154を使用して接着固定した。粘性が低いため作業性が優れ、強力な接着力を持ち、屈折率も1.54と優れた特性を備えている。
4)二次切断
スライドグラスに接着したチップを二次切断機(オートカッター)で約0.5㎜~0.7㎜の厚さに薄くスライスする。
5)第2次研磨
第1次研磨とほぼ同じ要領で、行程を進めていく、乱暴な研磨は、試料の剥離を招く、あくまでも、試料を平滑に研磨するように注意する。
研磨材(3000#)で偏光顕微鏡下で、試料の干渉色を見ながら。薄片の中の石英や長石が、淡灰白色~白色を呈するとき、(黄色を帯びるときは、やや厚い)をもって、仕上のメドとする。この場合の試料の厚さは、標準の0.02~0.025㎜である。(図4a,
b)
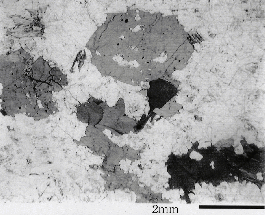
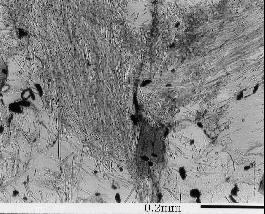
(図4) a. 花崗岩の顕微鏡写真 b. 片麻岩の顕微鏡写真
6)EPMA試料の作製はメノウ板研磨(3000#)で研磨材を補給しないで20分程度研磨その後、ダイヤモンドペースト0~0.025μで表面が鏡面になるまで磨く。
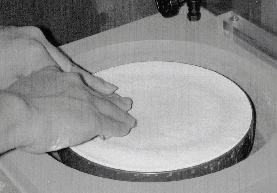
(図5)ダイヤモンド研磨機(岩石・鉱物等で研磨時間に差が出る)
試験結果
花崗岩の新鮮な部分ではレジンの浸透は明瞭には確認できず、堆積岩に比べ緻密であることが理解できる。しかし、部分的にはクラックが発達した部分があり堆積岩とは空隙構造を異にする。
また、花崗岩を構成する鉱物粒子のうち(1)石英にはシャープな直線的クラックが、(2)長石類にはネットワーク状の微細な空隙構造(図6)が、(3)黒雲母には劈開にともなう数ミクロンスケールの空隙構造が、紫外線を用いた顕微鏡観察で確認することができた。とくに、空隙の存在は断層運動などに伴う物理的なダメージを受けた岩石試料で明瞭に観察できる。
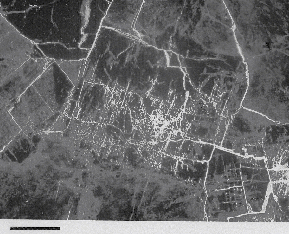
(図6)試料は岐阜県付知町の阿寺断層近傍の花崗岩中のカリ長石(スケールは2mm)
考察
(1) 試験結果として、花崗岩中の微小空隙(割れ目)の同定に有効である。
(2) 蛍光レジンの注入によって数ミクロンオーダーでの物質移動現象を明らかにできる可能性がある。
(3) 花崗岩中の物質移動に寄与していると考えられるいくつかの特徴的な空隙構造を抽出することができた。